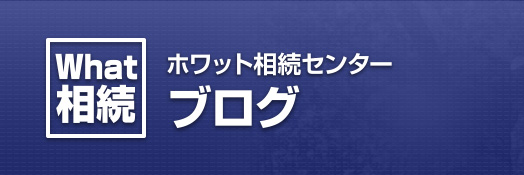2024年7月19日
生前に勤めいていた会社の未公開株式を、被相続人が持っている場合があります。
その場合の相続手続きを説明します。
未公開株式を相続した相続人が、その会社に対し権利行使をするためには、株主名簿の名義書換をしなければならず、会社に対して名義書換を請求することができます。
請求方法は、会社によって異なりますので、まずは、必要書類の確認など問合せをしましょう。
一般的な必要書類としては、被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍一式(又は法定相続情報)、印鑑登録証明書、遺言書又は遺産分割協議書、株券が発行されている場合は株券です。
中小企業の場合、名義書換請求に慣れていないケースが多く、名義書換から譲渡(売却)まで時間が掛かります。
それと、年1回の株主への事業報告書を作成していない会社も多く、相続税評価の算出にも苦労します。
未公開株の評価出しは複雑ですので税理士に相談しましょう。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「未公開株式手続き」はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
お問い合わせはこちらから⇒お問い合わせフォーム
2024年6月28日
証券会社も金融機関手続と同様、相続人が自分の相続分だけを単独でもらうことはできません。また、契約者(被相続人)の死亡を知った時点で証券口座の凍結を行います。
原則として、遺言書、遺産分割協議書、調停調書もしくは審判書によって手続きをするか、各証券会社が用意した相続届などの書面を使用して名義書換などの手続きを行います。
経験上、各証券会社(大和証券、みずほ証券、SMBC日興証券、野村證券、東海東京証券、岡地証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券など)に提出する書類はほとんど同じです。主なものとしては、被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍一式、相続人全員の戸籍及び印鑑登録証明書、窓口へ行く人の本人確認資料(免許証など)です。
ちなみに、すべての書類が揃ってから名義書換に有する時間は、平均1ヶ月です。
注意点として、銀行の手続きとは違い被相続人が口座開設している証券会社に相続する人の証券口座がなければ手続きができません。証券口座を持っていなければ、相続手続きと一緒に口座開設をしましょう。株式が相続人に名義変更された後、売却して金銭換価することができます。
なお、遺産分割協議書の記載内容によっては、一旦、株式を代表相続人に移しておき、金銭換価してから、葬儀寺院費用、未払医療費、その他費用を差し引いて金銭分割する事もできます。このような遺産分割協議書作成をご希望の場合はご相談下さい。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「証券口座手続き」はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
お問い合わせはこちらから⇒お問い合わせフォーム
2024年6月27日
金融機関は預金者(被相続人)の死亡を知った時点で預金口座の凍結を行います。
凍結されると、引き出しはもちろんのこと、入金や振替もできなくなります。
原則として、遺言書、遺産分割協議書、調停調書もしくは審判書によって手続きをするか、各金融機関が用意した相続届などの書面を使用して払戻しなどの手続きを行います。
経験上、各金融機関に提出する書類はほとんど同じです。
主なものとしては、被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍一式、相続人全員の戸籍及び印鑑登録証明書、窓口へ行く人の本人確認資料(免許証など)、通帳(定期預金証書含む)、キャッシュカードです(出資している場合は出資証券も必要)。
以下、豊橋市、豊川市、田原市、新城市、蒲郡市、岡崎市にある金融機関手続のマメ情報を掲載します。参考としてご覧下さい。
①豊橋信用金庫は相続人の住民票が必要な場合があります。
②豊川信用金庫、岡崎信用金庫は、相続担当部署(本店)とのやり取りとなります。
③ゆうちょ銀行は、各店舗がゆうちょ銀行代理店としての書類提出窓口になるだけで、書類チェックや口座解約は、ゆうちょ銀行相続センターがまとめて行っています。その関係で不足書類や訂正書類のやり取りはセンターと行わなければならず、面倒だと文句を言われる人が多いです。すべての書類が揃ってから解約まで平均2週間かかります。
④三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、みずほ銀行などの都市銀行は、すべての書類が揃ってから解約まで平均2週間かかります。
⑤名古屋銀行、静岡銀行、中京銀行、十六銀行、愛知銀行などの地方銀行は、すべての書類が揃ってから解約まで平均1週間かかります。
⑥JA(農業協同組合)は、預金者の大半が出資しているので、預金解約と一緒に出資証券の手続きも行いましょう。すべての書類が揃ってから預金解約までは1〜2日で終わります。出資の譲渡または解約(現金化)には1ヶ月以上の時間がかかります。
なお、遺産分割協議書の記載内容によっては、一旦、解約金を代表相続人に集めておき、そこから葬儀寺院費用、未払医療費、その他費用を差し引いて分割する事もできます。このような遺産分割協議書作成をご希望の場合はご相談下さい。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「銀行口座手続き」はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
お問い合わせはこちらから⇒お問い合わせフォーム
2024年6月26日
遺産分割の方法には、大きく分けると現物分割、代償分割、換価分割、共有分割がります。どの分割方法であれば合意できるのか話し合うことです。以下で各分割方法を説明します。
現物分割・・・A不動産は長男、B不動産は二男、C不動産は長女、というように相続します。
代償分割・・・長男1人が不動産のすべてを相続した代わりに、長男は二男及び長女に対し代償金として金銭を支払うという方法です。ただし、長男が代償金を払うだけの資産を持っていなければ債務不履行となり、金銭をもらえない可能性があります。債務不履行になっても遺産分割協議はやり直せませんので注意しましょう。
換価分割・・・不動産を相続人全員で共有取得し、その上で共有不動産を売却し金銭換価する方法です。代償金の支払能力のある相続人が存在しなかったり、不動産をほしがる人がいないなどの理由で選択されるケースが多いです。
共有分割・・・不動産を相続人全員で共有取得する方法です。二次相続などを考えると、所有者がどんどん枝分れしていき、譲渡や権利設定をしたいときに面倒となるので、あまりおすすめはしていません。
なお、代償分割、換価分割による遺産分割協議書は、様々な作成方法があります。この分割方法を希望される場合はご相談ください。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「遺産分割協議書の作成」はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
お問い合わせはこちらから⇒お問い合わせフォーム
2024年4月10日
「家族信託」の問合せが増えています。
信託スキームの説明、契約書作成、金融機関口座開設サポート、不動産信託登記サポートなどを行います。
ご興味のある方はご相談ください。